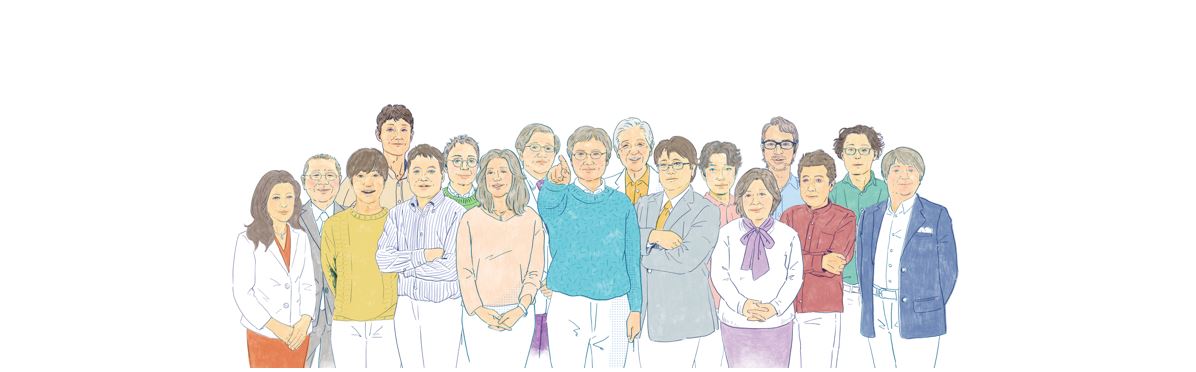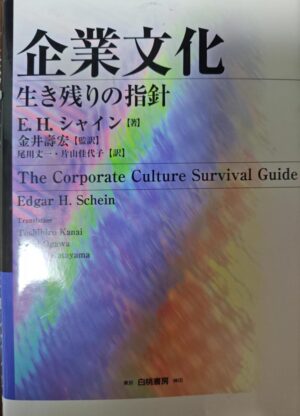データ分析の現場で、「課題がどうも『ふわっとしてる』なあ…」と感じることがあります。これは、解決すべき問題の本質や目指すべきゴールが曖昧で、具体的な分析アクションに落とし込めない状態を指します。このような状況を非常にもどかしく感じる方も多いでしょう。
こうした状況への一つのアプローチとして、「数値を分解する」ことがよく推奨されます。例えば、「売上を上げたい」という漠然とした要望に対し、「売上」を「客数 × 客単価」に分解し、さらに「客数」を「新規顧客 × リピート顧客」…といった具合に細分化していく手法です。
しかし、そもそも課題が「ふわっとしている」場合、その課題を示す言葉自体に「売上」のような定量化しやすい要素が含まれていないことも少なくありません。
そんな時、「言葉そのものを分解する」というアプローチが、突破口を開く鍵となることがあります。
例えば、「顧客理解を深めたい」というテーマも、分析プロジェクトでよく耳にしますが、これだけではどこから手をつければ良いか分かりにくいものです。そこで、「顧客理解」という言葉を構成する要素を分解してみます。すると、「プロフィール(デモグラフィック情報)」「インサイト(心理・価値観)」「行動パターン」「抱えている課題・ニーズ」「情報収集・意思決定プロセス」といった切り口が見えてきます。このように言葉を分解し、どの要素の解像度を高めることが、依頼者の真の目的達成や次の具体的なアクションに繋がるのかを考えることで、データ分析で何を明らかにすべきかが見えてくるのです。
この「言葉を分解して本質に迫る」思考法が、普段の生活でテレビや新聞等に接している中で、ふと有効だと感じたことがありました。
3月31日にフジテレビが公表した第三者委員会の報告書や、それに関連する一連の報道に触れていた時のことです。
(事件そのものへの言及はここでは避けますが)報道や数々の会見の中で「企業文化」や「企業風土」といった言葉が頻繁に使われていました。しかし、その多くが、何かを語っているようでいて核心を突いていない、いわば「バズワード」のように響き、私の中に強い違和感が残りました。表層的な言葉だけが飛び交い、問題の本質が見えにくくなっているように感じたのです。
このモヤモヤとした感覚を解消したいと思い、この機会に「企業文化」という言葉を自分なりに分解し、深く理解しようと考えました。そこで手に取ったのが、企業文化研究の第一人者、エドガー・シャイン氏の著書「企業文化」でした。
シャイン氏の理論で特に有名なのが、企業文化を3つのレベルで捉えるフレームワークです。
• レベル1:文物(人工物):目に見える組織構造および手順。
• レベル2:標榜されている価値観:戦略、目標、哲学。
• レベル3:潜在的な基本的仮定:無意識の当たり前の信念、認識、思考および感情
レベルが深くなるほど、より無意識的で、文化の本質を形作っている要素とされます。
シャイン氏は、最も深いレベル3について、「集団として獲得された価値観、理念、仮定であり、組織が繁栄するにつれて当然視されるようになったもの」と同著で述べています。この定義から重要なのは、レベル3を理解するためには、現在「当たり前」とされている無意識の仮定だけでなく、それが「集団として獲得され」「組織が繁栄するにつれて」当たり前になっていった「経緯」、つまりその文化が形成されてきた歴史的背景を知ることが不可欠だということです。
このシャイン氏のフレームワーク、特に「3つのレベル」と「経緯の重要性」という視点を持つことで、本記だけで267ページ、資料や要約版も含めると400ページ近い膨大な量と評された第三者報告書の内容が、驚くほど整理しやすくなりました。「バズワード」を分解し、構造化するフレームワークの力を改めて実感した瞬間でした。
このフレームワークに沿って報告書や関連報道を読み解くと、レベル3の「潜在的な基本的仮定」として現れているであろう「ハラスメント対応の不備と被害者軽視」「取引先中心の接待文化」「意思決定の硬直性」といった事象については多くの言及があるように思えました。しかし、それらがなぜ、どのようにして「当たり前」として組織に根付いていったのか、その「経緯」についての掘り下げが浅いように感じられました。これこそが、私が一連の報道に覚えた違和感の正体だったのです。(報告書の調査対象期間が2016年4月からと限定されていたこと、報告書の主目的があくまでも事件への会社組織の関与を明らかにすることであったことなどが、この点に影響しているのかもしれません。)
シャイン氏の著書「企業文化」では、文化を評価(アセスメント)する方法だけでなく、文化を変革する方法についても述べられていますが、「経緯」を理解する重要性は文化変革についての指摘を読むことでより強く感じられました。
成熟した企業の文化変革において、シャイン氏は「機能不全になったように見える文化的要素をいかに変革するかだけでなく、文化がどのようにして変革プロセスを助けられるかを判断しなければならない」「もし招聘されてくる人物が既存の文化を理解していなければこれは危険なことである。新しい最高経営責任者が、過去にその組織の一員であったとか、何らかの関わりがあるために既存の文化にある程度馴染みのある混成種の経営者であれば、企業再生が成功しやすい」と同著で述べています。これは、単に既存の文化を否定して新しいものを持ち込むのではなく、現在作用している文化の力学とその形成経緯を深く理解し、それを変革の推進力として活用することの重要性を示唆しています。ここでもやはり、「経緯」を知ることの重要性が浮かび上がってきます。
この視点を持つと、今後のフジテレビの「再生」に関する報道を見る際にも、「旧来の文化(ハラスメント軽視など)を単に断罪・否定するだけでなく、組織に根付いて作用している文化(とその経緯)を理解した上で、それを新しい価値創造にどう活かそうとしているか?」という観点を加えることで、より興味深く、より本質的な変化を見極めることができるでしょう。
このように、「企業文化」という一見捉えどころのない言葉をシャイン氏の著書を踏まえて分解してみることで、
• 膨大な情報のポイント整理
• 今後の動向を見る上での本質的な着眼点
を、単なるバズワードとして捉えていたときよりも(自分なりの解釈ではありますが)格段に高い解像度で捉えられるようになりました。
「言葉を分解し、その構造理解を試み、本質に迫る」。これは、データ分析の世界に留まらず、ビジネス全般において問題の本質を発見し、効果的な解決策を導き出す上で、私たちが常に磨き続けるべき、極めて重要な思考スキルであると、改めて強く感じています。